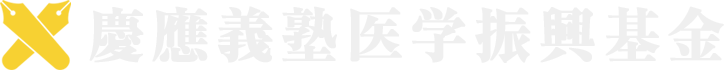第12回(2007年)受賞者
Brian J. Druker 博士

Investigator, Howard Hughes Medical
Institute
Director, Oregon Health & Science
University Cancer Institute
授賞研究テーマ
慢性骨髄性白血病に対する分子標的薬の開発
慢性骨髄性白血病(CML)は、フィラデルフィア染色体と呼ばれる染色体転座により生じたBcr/Abl融合遺伝子に起因すると考えられていたが、近年まで、時に致死的で重篤な副作用を伴う同種造血幹細胞移植以外には有効な治療法がない難治疾患であった。Druker博士は、Ablチロシンキナーゼ阻害剤である低分子化合物imatinib (Gleevec®)をCML治療薬として、製薬企業と共同で開発した。Druker博士は 開発初期よりimatinib がCML治療薬になる可能性に気づき、治験による臨床評価の原動力となった。imatinib は、CMLのみならずGIST(消化管間質腫瘍)など他の腫瘍にも強い抗腫瘍効果を示すことが明らかになっており、難治がん患者のQOLを大きく改善した功績は大きい。近年、抗腫瘍効果の検討から生まれた既存の抗がん剤とは異なり、がん生物学研究から予測された標的に焦点を当てて開発するという分子標的薬の開発が盛んに進められているが、経口服用可能で、副作用が少なく、ほとんどのCML症例に対して完全緩解導入可能なimatinib開発の成功は、今日のがん分子標的治療の潮流を築いた。がん治療薬の新機軸を明確にしたDruker博士の画期的業績は、慶應医学賞授賞に相応しい。
略歴
- 1977年
- B.A., University of California, San Diego, CA
- 1981年
- M.D., University of California School of Medicine, San Diego, CA
- 1981年
- Internship and Residency in Internal Medicine
Barnes Hospital, Washington University School of Medicine,
St. Louis, MO - 1984年
- Fellowship in Medical Oncology
Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA - 1987年
- Instructor in Medicine
Harvard Medical School, Boston, MA
Clinical Associate
Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA
Associate Physician
Brigham and Women's Hospital, Boston, MA
Medical Director
Nashoba Community Hospital, Oncology Clinic, Ayer, MA - 1993年
- Staff Physician
University Hospital and Clinics, OHSU - 1993年
- Associate Professor
Department of Medicine, Oregon Health & Science University
(OHSU) - 1993年
- Co-Director
Center for Hematologic Malignancies, OHSU Cancer Institute - 1993年
- Joint Appointment
Department of Cell and Developmental Biology, OHSU - 1993年
- Program Leader
Hematologic Malignancies, OHSU Cancer Institute - 1996年
- Joint Appointment
Department of Biochemistry and Molecular Biology, OHSU - 1996年
- Director / Associate Director
OHSU MD/PhD Program - 2000年
- Professor of Medicine
Division of Hematology & Medical Oncology, OHSU - 2002年
- Investigator
Howard Hughes Medical Institute - 2007年
- Director
OHCU Cancer Institute - 2007年
- Interim Chief
Division of Hematology & Medical Oncology:Hematologic
Malignancies
満屋 裕明 博士

熊本大学大学院医学薬学研究部
血液内科学 教授
授賞研究テーマ
エイズ治療薬の開発
20 世紀末に出現したacquired immunodeficiency syndrome (AIDS)が世界にもたらした恐怖と被害はきわめて甚大であった。満屋裕明博士は、その危険性にもかかわらず、1984 年、米国NIH Samuel Broder 博士の研究室で、自ら樹立したCD4 陽性ヘルパーT 細胞を用いて、AIDS の原因であるhuman immunodeficiency virus (HIV)に対する治療薬の研究・開発を開始、1985 年にレトロウイルス逆転写酵素を標的とした世界最初の抗HIV薬AZT(アジドチミジン)を報告、遂にその臨床開発に成功した。その後、ddI と ddCを発見・開発し、これらはAIDS 治療薬として世界中で臨床使用されている。さらに、最近、難治性AIDS に対して、新規プロテアーゼ阻害薬の開発にも成功している。現在、AIDS 治療においては 満屋博士が開発した薬剤を含めた多剤併用療法(HAART 療法)により、患者の予後は格段に向上している。満屋博士は、世界で最初のAIDS 治療薬AZTを開発し、その後もAIDS 治療薬開発に関して、世界的なオピニオンリーダーとして活躍しており、その業績は慶應医学賞授賞に相応しい。
略歴
- <学歴・職歴>
- 1975年
- 熊本大学医学部卒業
- 1980年
- 熊本大学医学部第二内科助手
- 1982年
- 医学博士(熊本大学医学部)
- 1982年
- 米国国立癌研究所客員研究員 (Visiting Fellow)
- 1984年
- 米国国立癌研究所上級研究員 (Cancer Expert)
- 1989年
- 米国国立癌研究所主任研究員 (Senior Investigator)
- 1991年
- 米国国立癌研究所、臨床癌プログラム
内科療法部門レトロウイルス感染症部部長 - 1997年
- 熊本大学医学部内科学第二講座(現血液内科・膠原病内科)教授
- 1999年
- 熊本大学医学部付属病院治験支援センター長(兼任)
- 2000年
- 熊本大学医学部付属病院感染免疫診療部長(兼任)
- 2000年
- 熊本大学医学部付属病院病院長補佐
- 2001年
- 熊本大学医学部付属病院副病院長
- 2003年
- 京都大学ウイルス研究所客員教授