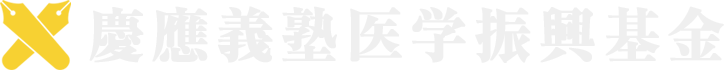第22回(2017年)受賞者
John E. Dick 博士

トロント大学 分子生物学教授、
プリンセス・マーガレットがんセンター
(カナダ)シニアサイエンティスト
1954年7月31日生まれ
授賞研究テーマ
がん幹細胞の同定
組織幹細胞は自分と同じ細胞を作り出す自己複製能と様々な細胞に分化する多分化能を有し、組織中の全ての細胞を供給する大本となる細胞です。がん組織にもこのような幹細胞が存在し、それを頂点とする階層性の構造があるという概念、つまり「がん幹細胞仮説」が古くから提唱されていましたが、その実態は不明でした。ジョンE. ディック博士は、免疫不全マウスにヒト白血病細胞を移植する実験モデルを用い、白血病においてがん幹細胞が存在することを世界で初めて証明しました。ディック博士は、白血病細胞の中から造血幹細胞に発現している表面マーカーを持った細胞を選別して免疫不全マウスへ移植したところ、百分の一以下の細胞数で、ヒト白血病をマウスで維持できることを見いだしました。このことは、ヒト白血病の中に、強い腫瘍原性と自己複製能を持つ細胞群が存在すること、すなわち、白血病にも正常の造血組織と同様に幹細胞が存在することを示しました。この研究を端緒として、がん幹細胞の概念が広く認知されるようになり、固形がんにもがん幹細胞が存在することが明らかになりました。がん幹細胞は通常のがん細胞に比べて治療に対する抵抗性が高く、がんの再発や転移の起源となる細胞です。がんの根治のためにはがん幹細胞を駆逐しなければならないという概念を生んだディック博士の功績は計り知れません。
略歴
- 1974年
- Registered Radiological Technologist,
Misericordia General Hospital - 1978年
- B.Sc. (Hons) Dept. of Microbiology, University of Manitoba
- 1984年
- Ph.D. Microbiology and Biochemistry, University of Manitoba
- 1978年-1984年
- Graduate Student, Dr. J. Wright, Department of Microbiology
and Manitoba Institute of Cell Biology,
University of Manitoba, NSERC Scholarship, MHRC Scholarship - 1984年-1986年
- Post-doctoral Fellow, Dr. A. Bernstein,
Ontario Cancer Institute and Mount Sinai Hospital, Research Institute, University of Toronto MRC Post-doctoral Fellowship - 1986年-1991年
- Scientist, Department of Genetics,
Research Institute Hospital for Sick Children, Toronto - 1987年-1991年
- Assistant Professor, Department of Molecular and Medical
Genetics, University of Toronto, Toronto - 1989年-1996年
- Research Scientist of the National Cancer Institute of Canada
- 1991年-1995年
- Associate Professor, Department of Molecular and Medical Genetics, University of Toronto
- 1991年-2002年
- Senior Scientist, Department of Genetics, Research Institute, Hospital for Sick Children, Toronto
- 1995年-現在
- Professor, Department of Molecular Genetics, University of Toronto
- 1996年-2001年
- Medical Research Council of Canada Scientist
- 2002年-現在
- Canada Research Chair in Stem Cell Biology,
Senior Scientist, Princess Margaret Cancer Centre,
University Health Network, Toronto - 2007年-現在
- Investigator, McEwen Centre for Regenerative Medicine,
University Health Network, Toronto - 2007年-2017年
- Director, Program in Cancer Stem Cells,
Ontario Institute for Cancer Research, (OICR), Toronto - 2017年-現在
- Director, Translational Research Initiative in Leukemia,
Ontario Institute for Cancer Research, (OICR), Toronto
受賞者からのメッセージ
多大なる感謝とともに、ここに慶應医学賞を謹んでお受けいたします。科学というものは他者との関わりなしに成し遂げられるものではありません。私は、トロントにおいて、素晴らしい同僚たちに恵まれ、非常に幸運でした。彼らは、科学的思考の最高水準を求め、それが、私にとって、常に厳格かつ明確な考え方で生物学的課題に取り組む、大きな原動力となりました。正常なヒト幹細胞と白血病のヒト幹細胞についての生物学に関して私たちが成し遂げたすべての研究は、多くの学生や博士研究員(ポスドク)たちが、このことについて思考し、実験の結果を得ることに多大な貢献をしてきたことにより蓄積された努力の賜物です。私は彼らにこの賞を捧げたいと思います。
小川誠二 博士(おがわせいじ)

東北福祉大学 感性福祉研究所 特任教授
1934年1月19日生まれ
授賞研究テーマ
機能的MRIの開発
小川誠二博士は、脳血流中の酸素濃度に依存した信号をMRI(核磁気共鳴画像法)装置で撮像できることを発見し、BOLD(Blood Oxygenation Level Dependent)信号と名付けました。さらに小川博士は、BOLD信号によって課題遂行中のヒト脳活動部位を撮像できることを実証し、機能的MRIの基本原理を確立しました。機能的MRIを用いることで、放射性同位元素などを用いることなく、ヒト脳活動を非侵襲的に繰り返し画像化することが初めて可能となりました。機能的MRIには全脳の活動を画像化できる特徴があります。そこでそれぞれの脳部位がどのような機能に関連するのか脳機能局在を調べるだけでなく、広範囲の脳活動を同時に読み解く新しい解析法も提案されています。解析技術の発展に加えて、MRI装置の性能向上や通信技術の発展に伴うデータ共有など近年の技術革新によって、機能的MRIは脳機能解析の中心的なツールとして活躍しています。ヒト脳情報の読み取りを目指した研究や精神疾患のバイオマーカーを同定する試みなど、機能的MRIの適用範囲は今後ますます拡大すると考えられることから、これらの基盤技術を開発した小川博士の貢献は極めて大きいといえます。
略歴
<学位>
- 1957年3月
- 東京大学工学部 応用物理 BS
- 1967年5月
- スタンフォード大学 化学科 PhD
<職歴>
- 1962年
- メロン研究所 放射線化学研究部 研究アソシエイト
- 1967年
- スタンフォード大学化学科 博士研究員
- 1968年-1983年
- ベル研究所 生体物理学研究部研究員、主任研究員
- 1984年-2001年
- ベル研究所 特別研究員、生体物理学研究部/生物演算研究部
ルーセントテクノロジー - 2001年-2004年
- ヨシバ大学 アルバート アインシュタイン医学部客員教授
- 2001年-2008年
- 財団法人濱野生命科学研究財団、小川脳機能研究所所長
- 2008年-現在
- 東北福祉大学 感性福祉研究所 特任教授
- 2008年-2012年
- 慶應義塾大学大学院 社会学研究科 訪問教授
- 2008年-2013年
- 韓国嘉泉医科学大学神経科学研究所 訪問教授
- 2011年-2015年
- 独立行政法人情報通信研究機構 R&Dアドバイザー
受賞者からのメッセージ
この度の名だたる慶應医学賞受賞という栄誉は、これまでに受賞されたご高名の諸先生方の列に加えて頂けるという名誉と共にこの上なき喜びであります。二十数年前に、ちいさな科学の基礎研究の内に出逢った現象が脳科学研究の場を大きく広げるのに役立ったとは、当初の期待を遥かに凌ぐものです。この脳機能画像化の分野の進展は世界中の数多くの優れた研究者達の努力の賜物です。また当初あまり考慮もしていなかった社会への還元というテーマが満たされつつある事には科学の力を感じます。